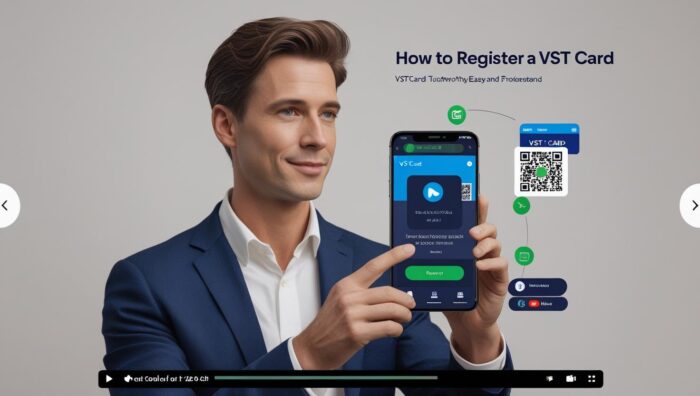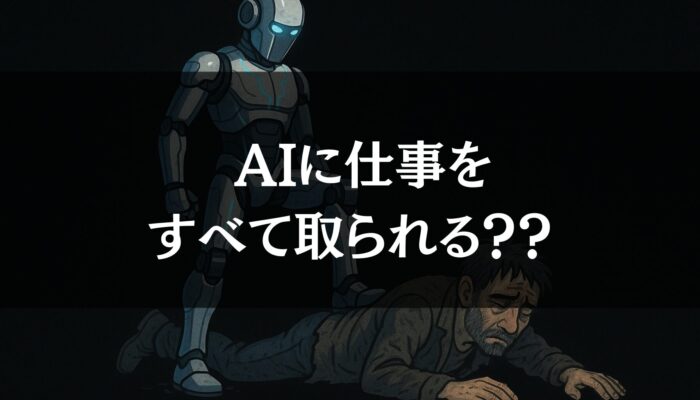もくじ
第1章 VSTとは何ですか?その仕組みと特徴

まず最初に押さえておきたいのが VSTとは何か という点です。VSTは「Virtual Smart Transaction」の略称で、ブロックチェーンを活用した次世代型の決済・報酬システムを指します。
従来の電子マネーやポイントサービスは、発行元企業が中央管理する形をとってきました。しかし、VSTはブロックチェーン技術を基盤にしているため、取引履歴がすべて分散型ネットワークに記録され、透明性と安全性が非常に高いのが大きな特徴です。
また、VSTは単なる決済手段にとどまらず、「ブロックチェーンライブ」という新しい仕組みと連動しています。これは、ライブ配信を通じて収益を発生させ、その報酬をVSTとして受け取れる仕組みです。配信者にとっては、視聴者からのギフティングや投げ銭がすぐにVSTとして反映され、換金や利用がスムーズに行えるのが魅力となっています。
さらに、VSTの導入によって期待できるのは、参加者全員が収益構造の一部になれる点です。従来のプラットフォームでは、配信者が収益の多くを得て、視聴者はお金を払う側でした。しかしVSTの仕組みでは、視聴者も報酬還元の仕組みに組み込まれ、参加することで利益を得られる可能性が広がります。
例えば、あるライブ配信を視聴しながら応援していた人が、AIによる広告マッチングや視聴データの価値提供によってVSTを獲得できるといったケースです。これにより、配信者・視聴者・プラットフォームの三者が、よりフェアに利益を分配できるようになっています。
VSTの特徴まとめ
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | Virtual Smart Transaction(VST) |
| 技術基盤 | ブロックチェーン |
| 透明性 | 取引履歴を分散型で管理 |
| 主な活用 | ブロックチェーンライブでの報酬還元 |
| 利点 | 配信者と視聴者の双方が利益を得られる仕組み |
これまでの電子マネーや仮想通貨が「送金・決済手段」に特化していたのに対し、VSTは「エンタメと収益を融合させた次世代の経済圏」と表現できるでしょう。
🎥ここで理解を深めるために、VSTやVIIVAの解説動画をひとつご紹介します。
第2章|VIIVAとは?その仕組みと収益モデル

VIIVAは、VSTと連動する形で誕生したグローバル向けのオンラインビジネスプラットフォームです。参考記事によると、単なる通販サイトやポイントサービスではなく、ライブ配信・EC・コミュニティ運営を統合した「次世代のマーケットプレイス」と位置づけられています。
最大の特徴は、誰でもスマホ一つで「商品を持たずに販売できる」仕組みを実現していることです。従来のネットショップ運営では、在庫の仕入れや物流管理といった負担がありました。しかしVIIVAは、プラットフォーム側が商品や流通を担うため、ユーザーは販売活動に集中できます。つまり、在庫リスクゼロで参入できるのです。
さらに収益モデルもユニークです。VIIVAでの売上は、AIによる推薦システムとブロックチェーンの報酬分配機能によって、利用者へ正確かつ透明に還元されます。販売者だけでなく、ライブ配信を通じて商品を紹介したインフルエンサー、またその配信を応援した視聴者にも報酬が行き渡る仕組みが整備されている点が注目に値します。
→VSTカードの詳しい作り方はこちらのページで説明しています。
VIIVAの収益構造(概要)
| 立場 | 収益の得方 |
|---|---|
| 販売者 | 商品を登録し、ライブやECで販売。売上が直接収益に。 |
| 配信者 | 紹介報酬や視聴者からの投げ銭をVSTとして受け取れる。 |
| 視聴者 | 参加報酬やデータ提供によってVSTを獲得できる仕組み。 |
このように、VIIVAは「販売する人」「紹介する人」「応援する人」それぞれに利益が回る設計がなされています。従来のECでは一方向的だった収益の流れが、三者循環型に進化したといえるでしょう。
また、参考記事では「グローバル展開を視野に入れた成長市場」である点も強調されていました。特にアジア圏や北米市場において、ライブコマースは急速に普及しており、VIIVAはこの流れに乗る形で拡大が期待されています。
まとめると、VIIVAは単なるECではなく、ブロックチェーンライブ×AI×グローバルECの統合プラットフォームです。VSTと組み合わせることで、個人でも国境を超えたビジネスが実現可能になります。
第3章|VSTカードとは何ですか?AIカードとの違い

VSTカードとは、VSTの仕組みを日常的に使いやすくするために開発された「実物カード型デバイス」です。従来のクレジットカードやポイントカードのような見た目をしていながら、実際にはブロックチェーンウォレットとAI機能を兼ね備えています。
利用者はこのカードを通じて、ライブ配信で得た報酬の受け取りやECでの購入、さらには海外送金までをシームレスに行うことが可能です。つまり、金融・ショッピング・配信収益を一元化できる「オールインワンカード」といえるでしょう。
一方で「AIカード」と呼ばれるものは、主にAIアシスタントとしての役割が強調されています。AIカードは個人のスケジュール管理、翻訳、データ解析などに特化しており、必ずしも決済や報酬受け取り機能を持つわけではありません。
VSTカードとAIカードの違い
| 項目 | VSTカード | AIカード |
|---|---|---|
| 主な役割 | ブロックチェーンを利用した報酬受け取り・決済・送金 | AIを活用した情報処理・サポート機能 |
| 対象ユーザー | 配信者・EC事業者・海外展開を考える個人 | ビジネスパーソン・個人利用者 |
| メリット | 収益を直接受け取れる、即時換金性、国際利用が容易 | 生活や業務の効率化、翻訳や学習サポートが可能 |
| 技術基盤 | ブロックチェーン+金融システム | AIアルゴリズム・クラウドサービス |
このように、VSTカードは「収益を動かすカード」、AIカードは「知識を補うカード」と整理できます。両者は役割が異なりますが、今後は統合されて、収益管理+AIアシスタントを同時に実現する可能性も十分に考えられます。
→VSTカードの詳しい作り方はこちらのページで説明しています。
実際に利用する場面をイメージしてみましょう。ライブ配信で視聴者から得た投げ銭が即座にVSTカードへチャージされ、そのまま海外出張時のホテル決済に使える。さらにAIカード機能を兼ね備えていれば、現地言語の翻訳やビジネス文書作成を同時にアシストしてくれる──そんな未来がすぐそこまで来ているのです。
第4章|AI名刺とは何か?新しいビジネス活用の形

AI名刺とは、従来の紙の名刺や単なるデジタル名刺を超えて、AIを活用したインタラクティブな自己紹介ツールを指します。単なる連絡先の交換にとどまらず、相手に対して自動で情報を伝え、必要なデータを提供する仕組みを持っているのが大きな特徴です。
例えば、従来のQRコード付き名刺では「名前・会社名・連絡先」が中心でした。しかしAI名刺では、名刺を受け取った相手が読み込むと、自動的に自己紹介動画・事業説明・商品リンク・ライブ配信ページなどへ誘導することができます。さらに、AIが相手のプロフィールや興味関心を解析し、最適な情報を提示することも可能です。
このような仕組みはブロックチェーンライブやVSTカードとの親和性が高く、営業活動やネットワーキングの場で大きな差別化を生みます。単なる「連絡先の交換」から「即時にビジネスをスタートできる接点」へと進化しているのです。
AI名刺の特徴
- 紙ではなくスマホやデバイス上で動作するため、紛失リスクが低い
- AIが相手の興味に応じた情報を表示するため、営業効果が高まる
- 動画・ECサイト・ライブ配信への導線を名刺から直接つなげられる
- 利用データはブロックチェーンで管理され、透明性と改ざん耐性を確保
従来の「渡して終わり」の名刺とは違い、AI名刺はその後も継続的に情報を更新できる点が画期的です。名刺を受け取った相手に対して、後から新しいキャンペーンやイベント情報を届けることも可能になります。
また、VIIVAやVSTの仕組みと組み合わせることで、名刺がそのまま商品販売の入り口や報酬分配のきっかけになり得ます。営業・PR・マーケティングを一つに統合するこの仕組みは、今後のビジネスシーンで大きな武器になるでしょう。
第5章|ブロックチェーンライブとは?配信と収益の新常識

ブロックチェーンライブとは、その名の通り「ブロックチェーン技術」を基盤にした新しい形のライブ配信サービスです。従来のライブ配信は、配信者が投げ銭や広告収入を得て、その一部をプラットフォーム側に手数料として支払う仕組みが一般的でした。しかし、ブロックチェーンライブでは、配信者・視聴者・プラットフォームが公平に報酬を分配できる点が最大の特徴です。
配信者は視聴者から受け取ったギフティングや投げ銭を、即座にVSTとして受け取り、そのまま利用や換金が可能になります。さらに、単に配信者が利益を得るだけでなく、視聴者も参加することでVSTを得られる点が従来のライブ配信との大きな違いです。
→VSTカードの詳しい作り方はこちらのページで説明しています。
従来のライブ配信とブロックチェーンライブの違い
| 比較項目 | 従来型ライブ配信 | ブロックチェーンライブ |
|---|---|---|
| 収益の流れ | 配信者 → プラットフォームが手数料を差し引き → 残りが配信者 | 配信者・視聴者・プラットフォームに公平分配 |
| 透明性 | 中央管理で、分配の詳細が不透明な場合が多い | ブロックチェーンに記録され、透明性と改ざん耐性を確保 |
| 視聴者のメリット | 応援のための課金のみでリターンはなし | データ提供や参加によってVSTを受け取れる |
このように、ブロックチェーンライブは「見る人」「発信する人」双方に利益をもたらす新しい収益モデルです。結果として、参加者のモチベーションが高まり、コミュニティがより活発になるのです。
また、配信の内容も多様化しています。エンタメ系の配信だけでなく、教育・ビジネス・商品販売などにも活用されており、ライブ配信を通じて商品を紹介・販売するライブコマースとの親和性が非常に高い点も特徴的です。
例えば、配信者が商品を紹介し、視聴者がその場で購入すると、売上の一部がブロックチェーン上で即時に分配されます。これにより「配信を楽しみながら収益が循環する仕組み」が実現しているのです。
まとめると、ブロックチェーンライブは「透明性・公平性・参加型収益」をキーワードに、これからのエンタメ・教育・EC分野で中心的な役割を果たす可能性があります。VSTやVIIVAと組み合わせることで、配信者も視聴者も「稼ぎながら楽しむ」世界が広がるのです。
第6章|VSTとVIIVAを活用した収益化の実例と可能性

VSTとVIIVAを組み合わせることで、従来の副業やECでは実現できなかった新しい収益モデルが生まれています。ここでは具体的な実例を交えながら、その可能性を見ていきましょう。
実例1:ライブ配信+EC販売の融合
ある配信者は、ブロックチェーンライブを活用して美容関連商品を紹介しました。視聴者はその場で購入でき、配信者は販売手数料と投げ銭をVSTとして即時に受け取りました。さらに、購入を促した視聴者の一部にも参加報酬が配布され、結果として「売る人・紹介する人・買う人」の全員に利益が循環しました。
実例2:グローバル展開の容易さ
VIIVAは海外市場への参入を容易にします。例えば日本の小規模ブランドがアジア向けに商品を販売する場合、従来は物流や決済の壁が大きなハードルでした。しかしVSTカードを通じた即時決済と、VIIVAの国際流通網により、在庫を持たずに海外の顧客へ商品を届けることが可能になっています。
実例3:AI名刺を使った営業活動
営業担当者がAI名刺を利用すると、名刺を受け取った相手はその場で企業紹介動画や製品ページにアクセスできます。そこからブロックチェーンライブ配信につながり、商品の詳細をライブで体験。購入が発生すると報酬がVSTとして即座に分配される──こうした流れは、従来の営業プロセスを大きく短縮する可能性を秘めています。
→VSTカードの詳しい作り方はこちらのページで説明しています。
期待される収益の広がり
- コンテンツ配信者:投げ銭+商品販売+広告収益を多重に獲得
- 個人事業主:在庫を抱えずにグローバル販売が可能
- 視聴者:参加型リワードで小さな収益を積み上げることができる
このように、VSTとVIIVAの組み合わせは「収益の機会を一部の人からすべての人へ広げる」ことを実現しています。特にブロックチェーンライブの仕組みを核とすることで、透明性のある収益循環が可能になり、従来の一方通行型モデルから「参加型エコシステム」へと進化しているのです。
将来的には、教育・ヘルスケア・地域活性化といった分野にも応用されることが期待されます。例えば、教育者が配信で講座を行い、参加者が学びながら報酬を得る仕組みや、地域の特産品をライブで紹介し即時販売するケースなど、多様な活用が考えられます。
第7章|VSTは安全なのか?リスクと注意点

VSTやVIIVAは大きな可能性を秘めていますが、導入や利用にあたってはいくつかのリスクや注意点も存在します。ここでは、安全性の観点から整理していきましょう。
1. 暗号資産としての価格変動リスク
VSTはブロックチェーン上で流通するトークンとして扱われるため、一般的な暗号資産と同様に価格変動のリスクを伴います。例えば、ライブ配信で得た報酬が翌日には価値が下がる可能性もゼロではありません。そのため、収益の一部は安定資産へ換金するなど、リスク分散を心がけることが重要です。
2. 技術的トラブルやセキュリティ問題
ブロックチェーン自体は高い透明性と改ざん耐性を持っていますが、利用者の端末やアプリに脆弱性がある場合は不正アクセスのリスクが残ります。VSTカードやウォレットを利用する際は、二段階認証やセキュリティ更新を徹底することが推奨されます。
3. 規制や法律面での変化
暗号資産やブロックチェーン関連サービスは、国ごとに規制や法律が異なります。将来的に法律が変わった場合、取引や利用方法に制限がかかる可能性も考えられます。特に海外展開を考える場合は、対象国の規制動向を確認することが欠かせません。
4. 過度な収益期待への注意
参考記事でも「月収1000万円以上稼げるチャンス」という表現がありましたが、これはあくまで成功事例です。誰でも同じ結果を得られるわけではなく、参入タイミング・努力・戦略によって成果は変わります。過剰な期待を持ちすぎず、長期的な視点で取り組むことが安全です。
安全に利用するためのチェックリスト
- 報酬を受け取ったら一部を安定資産に換金してリスク分散する
- 二段階認証・強力なパスワードでアカウントを保護する
- 常に公式アプリや公式ページからログイン・利用する
- 国や地域の規制変更に注意し、最新情報を把握しておく
→VSTカードの詳しい作り方はこちらのページで説明しています。
まとめると、VSTやVIIVAは新しい収益モデルを提供する一方で、暗号資産特有のリスクや規制の影響を受ける可能性があります。正しい知識と対策を身につければ、安心して利用しながら将来のチャンスを活かせるでしょう。
第8章|これから始める人へのステップとまとめ

ステップ1:公式情報の確認と登録
まずは公式サイトや正規のパートナーを通じて情報を収集しましょう。SNSや非公式サイトには誤情報も多いため、登録や契約の際は必ず正規ルートを利用することが大切です。
ステップ2:VSTカード・AIカードの準備
収益を受け取るためにはVSTカードの発行が推奨されます。これにより、ライブ配信やEC販売で得た報酬をスムーズに受け取ることができます。AIカードを併用すれば、翻訳やデータ整理などのビジネスサポートも可能になり、活動効率が大幅に向上します。
ステップ3:小規模から実践
最初から大きな収益を目指す必要はありません。例えば、AI名刺を活用して自己紹介動画を配信し、少額の商品やサービスを紹介するところから始めるのがおすすめです。小さな成功体験を積み重ねることで、自信とノウハウが蓄積されます。
ステップ4:ブロックチェーンライブでの発信
次のステップはブロックチェーンライブを使った発信です。教育・エンタメ・商品紹介など、自分の得意分野で配信を行いましょう。参加者はVSTで報酬を得られるため、視聴者の満足度とリピート率が高まります。
ステップ5:グローバル展開への挑戦
VIIVAを活用すれば、在庫リスクなしで海外展開が可能です。特にアジア圏ではライブコマースの需要が急拡大しているため、海外市場を視野に入れた取り組みは今後の大きなチャンスとなります。
まとめ
VSTとVIIVAは、「配信する人」「応援する人」「商品を届ける人」のすべてが利益を得られる新しい経済圏を築いています。AIカードやAI名刺の導入によって、営業や日常業務までが効率化され、個人でも大きなビジネスチャンスを掴める時代がやってきました。
もちろん、リスクや規制への注意は欠かせません。しかし、正しい知識と準備をもって取り組めば、VSTとVIIVAは「稼ぐ手段」であると同時に「新しい働き方のスタンダード」になっていくでしょう。未来のチャンスを掴むのは、行動を始めた人です。
当サイトオススメの仮想通貨取引所
仮想通貨の取引を始めるのに必ず必要になるのが仮想通貨取引所! 国内、海外たくさんあってどれを使えばいいのか迷ってしまいますよね? そこでここで仮想通貨するなら開設しておいたほうがいい仮想通貨取引所を紹介していきたいと思います。Bybit
仮想通貨するなら最低ここは開設しておきたい!というのがBybit(バイビット)。 Bybitは2018年にシンガポールで設立された取引所です。 おそらくですが、日本人が使う海外取引所の中では一番ユーザーが多いです。 取引画面等も全て日本語に対応していてとても使いやすいです。当サイトからの登録で \最大30000USDTのボーナス!/
 日本語でのサポートにも対応、スマホアプリもあり、取引もしやすいです。
スプレッドも業界最小、最大500倍のレバレッジ、手数料も業界最小と悪いところがありません。
とりあえずBybitは開設しておきましょう。
日本語でのサポートにも対応、スマホアプリもあり、取引もしやすいです。
スプレッドも業界最小、最大500倍のレバレッジ、手数料も業界最小と悪いところがありません。
とりあえずBybitは開設しておきましょう。
MEXC
もう一つ、MEXCも開設しておいたほうがいい取引所の一つ。 Bybitとの違いはMEXCのほうがマイナーな通貨が上場して取引できるようになることがあります。 草コインで遊びたい方はMEXCはかなり使えますよ!